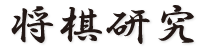中飛車
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 一 | |||||||||||
| 二 | |||||||||||
| 三 | |||||||||||
| 四 | |||||||||||
| 五 | |||||||||||
| 六 | |||||||||||
| 七 | |||||||||||
| 八 | |||||||||||
| 九 |
中飛車の駒組みの例
概要
中飛車は将棋の戦法の一つで、振り飛車に分類される。飛車を盤面中央の5筋に振ることから中飛車と名前がついた。
かつては振り飛車といえば、中飛車<四間飛車<三間飛車<向かい飛車の順で攻撃の要素が強くなるとされ、中飛車は守備に重きをおいた戦法とされていた。実際、ツノ銀中飛車は千日手も辞さないほど守勢の戦法である。しかしゴキゲン中飛車が登場し、より攻撃に重点をおく戦法が知られて爆発的に研究が進んだ(プロ・アマ問わず、攻める戦法は守る戦法よりも研究が進む傾向がある)。なお、角行・桂馬などを有効に使用できる戦法なので破壊力が高く、相手も中飛車で対抗すると総力戦となる。
中飛車全体の特徴として、飛車を5八(後手は5二)に振るので左金の活用が難しく、専ら左側を守ることが多い。ほとんどの場合で囲いに左金を利用しにくく、囲いが片美濃囲いなどになり固くならないために敵の飛車を自陣へ入れると致命傷になることが多い。そのため、自陣を効率よく守るバランス感覚が必要であるとされる。
相振り飛車においては、お互いに玉を右側に囲った場合に飛車の筋が相手玉よりも比較的遠くなり、自陣は左金の活用が難しい上に相手と比べて飛車と玉が接近した形となってしまう欠点がある。そのため他の振り飛車と比べて採用が少なく、逆に三間飛車は中飛車に対する有力な対策とされた。
中飛車の諸戦法
原始中飛車
別名を「下手の中飛車」といい、角道を止めてただ攻めまくるだけの戦法。
ツノ銀中飛車
バランスの良い構えで急戦策に強いが、玉が薄く居飛車穴熊など持久戦策の隆盛により衰退した。
風車
ツノ銀中飛車に近い駒組みで、飛車を一番手前の段に引く。
ゴキゲン中飛車
角道を止めない振り飛車であり、従来の中飛車に比べて積極的に攻勢をとることが出来る。後手番で多用される戦法であるが、先手番でも応用できる。
5筋位取り中飛車
序盤早々に5筋の位を取る。
カニカニ銀
急戦矢倉の一種で、銀を前線に送り出し、矢倉を組む過程で相手の対応によって中飛車に振る(振らない場合もある)。
矢倉中飛車
急戦矢倉の一種。主に後手番が相矢倉模様から中飛車に振り直す作戦で、先手が矢倉囲いを完成させる▲7七銀を優先した場合に生じた中央の薄さを突くのが狙いの作戦である。
平目
囲いにおいて、左金を中飛車の下(玉の初期位置)に移動するのが特徴。本来は「香落ち上手の戦法」として知られる。
中飛車左穴熊
中飛車であるが、居飛車のように玉を左側に穴熊に囲う戦法。相振り飛車のときに用いられる。
英ちゃん流中飛車
5筋の歩を突かないまま中飛車に振る。
銀多伝
「二枚落ち下手の戦法」の代表格。4筋の位を取って上手陣を圧迫し、5筋から攻めていく。