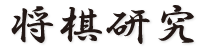矢倉3七銀
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 一 | |||||||||||
| 二 | |||||||||||
| 三 | |||||||||||
| 四 | |||||||||||
| 五 | |||||||||||
| 六 | |||||||||||
| 七 | |||||||||||
| 八 | |||||||||||
| 九 |
矢倉3七銀基本図
目次
概要
矢倉3七銀戦法は、相矢倉の24手目から25手目に▲3七銀と指すもので、相矢倉における主力戦法であり、森下システム、急戦矢倉、早囲いとともに、現代の相矢倉の序盤戦術の根幹になっている。
後手としては25手目▲3七銀に対し△6四角が半ば絶対手になる。この手を怠ると先手から▲3五歩△同歩▲同角とされ、▲4六角・3六銀型の理想的な攻撃陣を先手に許すことになる。
攻防に利く角で後手は攻撃陣を築きにくく、先手は3筋で手に入れた歩を活かして▲1四歩△同歩▲2四歩と仕掛ける。△2四同銀なら▲2五銀のぶつけから、△2四同歩には▲2五歩の継ぎ歩からいずれも仕掛けが成立する。1筋を絡めれば攻めが厚くなるのは当たり前だが、1筋を絡めなくても仕掛けは十分に成立する。端歩を突くのを省略して▲2四歩から仕掛けるのも有力である。
△6四角以後先手の作戦は、 雀刺し、棒銀、加藤流、4六銀・3七桂型(有吉流)に大別される。
メリット
- 容易に主導権を握り続けられる
加藤流
1990年代前半、勝率7割とも言われた森下システム全盛時にも独特のこだわりをもつ加藤一二三によって指され続けた息の長い作戦であり、今でも矢倉を得意とする居飛車党に愛用されている。当初は▲2六歩を早くから突く矢倉24手組からの移行であったが、現在は飛車先不突矢倉から組むことが多い。
▲2六歩 – ▲1六歩を決めた後に、相手が1筋を受けるか否かで対応を変える柔軟性が特長の戦型である。まず端を受けた場合、棒銀の形から▲1七香 – ▲1八飛の形にして攻め倒す。現在はこれで先手有利が確立している。
端を受けなかった場合、端を突き越してから▲3八飛と寄り、▲4六銀と出る機会を狙う。後手にある程度の選択肢があり、△7三銀から速攻に出る、△5三銀と守りを固め中央からの反撃を窺うなど手段は多い。それぞれの手順について定跡が確立している。▲3八飛と寄らず、場合によっては棒銀の形から▲3七桂 – ▲2七飛 – ▲1八香と組む場合もある。
矢倉4六銀・3七桂型(有吉流)
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 一 | |||||||||||
| 二 | |||||||||||
| 三 | |||||||||||
| 四 | |||||||||||
| 五 | |||||||||||
| 六 | |||||||||||
| 七 | |||||||||||
| 八 | |||||||||||
| 九 |
矢倉 4六銀・3七桂型
▲4六銀-▲3七桂として、▲2五桂からの仕掛けを狙う。
当初は、これに対して▲4六銀の瞬間に△4五歩と突いて▲3七銀と追い返す手が多く見られたが、この歩を伸びすぎとして▲4六歩と反発されて争点になるので、一度はほぼ消滅した。
その後、後手の対策は▲4六銀 – ▲3七桂 – ▲3八飛の理想形に組ませる間に△6四角 – △5三銀 – △7三角から△8五歩と突いて先手の攻めを待って反撃するものになり、場合によっては△4二銀右と引いてさらに固める。先手はそこでいきなり仕掛けると反撃が厳しく、矢倉穴熊に組み替えてから仕掛ける。後手が穴熊を嫌えば△8五歩でなく△9五歩とし、△8五桂から端に殺到する構想の森内流もあり、これに対し先手がなおも穴熊を目指すと敗勢に陥るという結論が出ている。また、すぐに仕掛けるのも面白くないことが分かり手待ちをするなど先手は苦戦していたが、▲6五歩と突く宮田新手によって態勢を立て直した。△7三角とされた後でも▲6五歩と突き、後手の理想形からわざと一手指させてそれを崩すのが目的で、他にも▲6四歩の突き捨てや▲6六角と据えるなどの手も見ている。▲6五歩には△6四歩の反発が気になるが、8五まで歩が伸びていないので成立しない。
この△8五歩と△9五歩が長年の主な対策として用いられてきたが、2013年頃から塚田泰明により前述した△4五歩の研究が始まり、菅井竜也が披露した△5五歩、さらに渡辺明が指した△9四歩と展開する手が発見され△4五歩が優秀ではないかと見直されてきた。確かに先手に反発されて争点はできるのだが、先手が攻めきるのも難しいという認識が生まれて、近年は4六銀・3七桂型そのものを先手が避ける傾向にある。2015年度の名人戦・棋聖戦では5局が矢倉戦となったが、いずれも先手は4六銀・3七桂型を選択せず、現在は藤井矢倉が選択される傾向が強まっている。