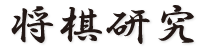石田流
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 一 | |||||||||||
| 二 | |||||||||||
| 三 | |||||||||||
| 四 | |||||||||||
| 五 | |||||||||||
| 六 | |||||||||||
| 七 | |||||||||||
| 八 | |||||||||||
| 九 |
石田流の駒組みの例
概要
石田流は将棋の戦法の一つで、三間飛車に分類される。
江戸時代中期に盲目の棋士・石田検校が生み出したといわれる。石田の実戦譜も残っているが、いずれも石田の負けに終わっている。
石田流対策としては棒金が有効であることもよく知られており、古川柳にも「尻から金とうたれで石田負け」(俳風柳多留、棒金で石田流が崩されて負けることと、小早川金吾(秀秋)に攻められて石田三成が関ヶ原の戦いで敗れたこととをかけた句)というものがあるほどである。
飛車を7六、桂馬を7七に配する構えを言う。角は基本的に9七が定位置である。振り飛車の理想形といわれ、最初から三間飛車に振らない場合にもこの形が現れることもままある(四間飛車やひねり飛車など)。
香落ち戦では特に石田流の構えが理想形となる。これは飛車が△3四にあることにより香のない1筋と下手の飛車先である2筋を守ると共に、左桂(△2一)の動きが自由になるためとされている。
居飛車穴熊対策としての石田流本組はいくつかの戦い方があり、有力な戦法として、左の金将を▲7八に置いて広く構え、手薄になった7筋を攻めるというものがある