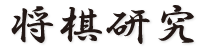角換わり
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| 一 | |||||||||||
| 二 | |||||||||||
| 三 | |||||||||||
| 四 | |||||||||||
| 五 | |||||||||||
| 六 | |||||||||||
| 七 | |||||||||||
| 八 | |||||||||||
| 九 |
角換わり戦法の例
概要
角換わり(かくがわり)は代表的な戦法の一つで、序盤で角を交換する戦法。
初級者から中級者にとっては、持駒の角を打ち込めるため自由度が高い戦法である。しかし上級者以上になると、双方ともに角の打ち込みを避けようと自陣に気を配るため、指し手が限定される。プロであればなおのことである。対局者のレベルが上がるほど変化の幅が狭く、横歩取りと並んで精緻な研究が進んでいる。
一般的に、先手が攻め込んで後手がカウンターを狙う。そのため、先手が攻め込むタイミングを外せば戦線膠着に陥り、千日手に至る。アマチュアにとってはつまらない展開だが、プロにとっては先手であること自体が僅かながら有利であるため、後手は千日手に持ち込めば作戦成功とみなされる。したがって「カウンター狙いの後手に対して、先手が攻めきれるのか」が数十年間研究され続けている角換わりのテーマである。先手の勝率が比較的高い戦法の一つであり、この戦法を得意とする代表的なプロ棋士として、谷川浩司や丸山忠久などが挙げられる。
だが近年では後手の研究も進み、先手も攻めきるのは簡単ではなくなってきている。
角換わりにおいては、5筋の歩をつくと△3九角(後手なら▲7一角)から馬を作られるなど、自陣に隙が生じやすい。そのため「角換わりには5筋を突くな」という格言がある。
最初の共通手順
▲7六歩△8四歩▲2六歩△3二金▲7八金△8五歩▲7七角△3四歩▲8八銀△7七角成▲同銀△4二銀と進む(昭和60年代までは5手目が▲2五歩だった)。途中、後手が角交換をして手損をしたように見えるが、先手が角を7七に動かした一手を無駄にしているので、双方手損はない。
先手の8八銀に対する後手の10手目で、△4二銀と変化することはできる。その場合、先手から▲2二角成と角交換をする。△同金の一手に、▲7七銀と進み、いずれ後手は壁金を解消する△3二金を指さなければならず、上述の手順と同型になる。
ここから角換わり棒銀・角換わり腰掛け銀などの戦法へと移行する。かつては角換わり早繰り銀という戦法も採用されていたが、最近のプロの実戦ではあまり見られない。
角換わりの諸戦法
木村定跡
初代実力制名人・木村義雄が発表した将棋の定跡。角換わり腰掛け銀のうち、先後同型角換わり腰掛り銀と呼ばれる戦型の定跡で、先手勝利まで研究が終わっていることから、完成された定跡とも言われている。
飛車先保留
歩を突かないことで、▲2五桂と跳ねる余地を作ったのである。この手の発見によって、専守防衛を狙った陣形でも先手から打開することが可能になったため、よりカウンターの攻撃力が高い戦型に回帰することになった。
後手番一手損角換わり
既出の図において、もしも△8五歩が△8四歩であれば結論が変わりうる。先手飛車先保留と同様で、後手に△8五桂と跳ねる手が生じ、カウンターの破壊力がさらに増すからである。しかし将棋には一手パスというルールが存在しないため、30手ほど先の手詰まりを見越して、序盤に後手が無理矢理角交換を行う。単に「一手損」とも呼ばれる。